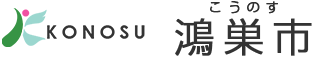本文
国指定重要無形民俗文化財「鴻巣の赤物製作技術」について
「鴻巣の赤物製作技術」が、玩具の製作技術で全国初、民俗技術で県内初の国指定重要無形民俗文化財に指定へ
「鴻巣の赤物製作技術」が、平成23年1月21日(金曜日)に行われた国の文化審議会(会長:西原鈴子)において、重要無形民俗文化財として指定するよう、文部科学大臣に答申されました。
これは、玩具の製作技術の重要無形民俗文化財指定としては全国初、民俗技術の国指定としては県内初となるものです。今回の指定により、県内の国指定重要無形民俗文化財は7件となります。
また、市内にある国指定文化財は、生出塚埴輪窯跡出土品(70点)と合わせて2件となります。

1 文化財の名称
鴻巣の赤物製作技術
2 所在地
鴻巣市
3 保護団体
鴻巣の赤物保存会
4 文化財の概要
「鴻巣の赤物製作技術」は、鴻巣市人形町に伝承される、桐の大鋸屑(おがくず)に正麩(しょうふ)糊(のり)を加えて練った桐塑(とうそ)製の生地を型に入れて成型し、赤く彩色した玩具を製作する技術です。
赤色は、かつて命に関わる子どもの病として恐れられた疱瘡(ほうそう)(天然痘)除(よ)けに起源を持つ魔除けの色であり、赤物にも子どもを守る効果が期待されていました。
赤物の製作は、まず、タネと呼ばれる木製の原型から松脂(まつやに)などを材料として釜型(かまがた)を作ります。この型に桐塑を詰めて生地抜きし、乾燥させてからバリトリ(生地のはみ出した部分を削り取る)をして成型します。
彩色は、胡粉(ごふん)を2度下塗りをした後、赤い顔料と膠(にかわ)を溶かした塗料の中に浸して着色(乾燥後にもう一度着色)し、最後に目鼻や模様などの細部が筆で描かれます。

釜型づくり

生地抜き

乾燥

胡粉塗り

赤塗り

面相描き
現在、主要な赤物はだるまや獅子頭で、大小様々なものが製作されていますが、かつては熊金(熊乗り金太郎)や鯉金(鯉抱き金太郎)など金太郎を題材としたものや天神、動物など数百種類が作られ、中山道などを通じて、関東地方を中心に広く各地に流通していました。
今回の答申は、赤物が子どもの無事な成長を祈願する民間信仰を背景として作り続けられてきたことや、大量生産の技術でありながらも全工程にわたって伝統的な製作技術が維持されている点などが評価されたものです。
重要無形民俗文化財とは
文部科学大臣が無形民俗文化財のうち特に重要なものを指定し、その保存と継承を図るもので、風俗慣習(「川越(かわごえ)氷川(ひかわ)祭(まつり)の山車(だし)行事(ぎょうじ)」など)、民俗芸能(「鷲宮(わしのみや)催馬楽(さいばら)神楽(かぐら)」など)、民俗技術の3種類に別けられます。
民俗文化財とは
民俗技術は、生活や生産に関する用具・用品などの製作技術など、地域において伝承されてきた技術のことです。
平成17年4月に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって、新たに民俗文化財に追加されました。
昨年度までに、千葉県木更津市の「上総(かずさ)掘(ぼ)りの技術」、富山県高岡市の「越中(えっちゅう)福岡(ふくおか)の菅笠(すげがさ)製作技術」など、10件が重要無形民俗文化財に指定されています。