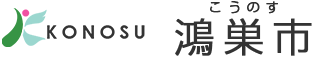本文
令和7年度施政方針及び予算(案)の大綱
令和7年3月定例会 令和7年度施政方針及び予算(案)の大綱
1 施政方針
(1)はじめに
本日ここに、令和7年度予算案及び関連諸議案のご審議をいただくにあたり、新年度の市政運営に臨む所信の一端を申し述べさせていただきます。
令和6年は、元日に最大震度7の「能登半島地震」、9月には奥能登を襲った豪雨が発生し、度重なる災害の影響により、今なお多くの方々が避難生活を余儀なくされております。本市では、石川県七尾市及び輪島市に職員と給水車を派遣したほか、募金活動などを通じて、いち早く被災地を支援してまいりました。災害派遣や報道などにより現地の状況を知るにつれ、万一の災害に対して、市民が「安全・安心」に暮らすことができる地域づくりのために、市が果たすべき役割や国土強靭化の重要性を改めて痛感したところです。
昨年は、昭和29年の市制施行から70周年を迎えた節目の年でした。「なないろの 笑顔咲かせる 鴻巣市」をキャッチコピーとして、市民の皆さんや100を超える70周年記念事業PRパートナー事業者との連携のもと、様々な記念事業や冠事業を実施したほか、10月1日の市民の日には「市制施行70周年記念式典」を挙行いたしました。これらの取組を通じて、これまで先人たちが築いてきた歴史や文化、まちづくりを改めて振り返ることで、未来に向け、夢と希望に満ちたまちづくりを進め、次の世代へと継承していくことの大切さと責任の重さを改めて実感した一年でした。
また、本市では、国が提唱する「こどもまんなか宣言」の趣旨に賛同し、未来を担う「のすっ子」たちが健やかで幸せに成長できる持続可能な地域社会の実現を目指す方針のもと、5月5日のこどもの日に「こどもまんなか応援サポーター」を宣言しました。
現在は、こどもまんなか社会の実現に向け、本市におけるこども・若者施策に関する計画として、本年3月の完成を目指し「鴻巣市こども計画」の策定を進めています。
さらに、令和6年度は、全市的なSDGsの推進に力を注いでまいりました。地域でのSDGs達成に向け、現在、81の事業者や団体が「こうのとりSDGsパートナー」に登録し、本市と連携した取組を進めているほか、7月に開催したSDGs未来会議では、市内8中学校の生徒が、SDGsの視点から地域課題について考え、持続可能なまちづくりに向けた提案を行いました。これらの取組を通じて創出・拡大してきた市民や事業者、学校等とのパートナーシップを基盤として、本年1月25日には、こどもから大人まで楽しくSDGsを学べる「こうのとりSDGsフェスティバル」を開催し、市内高校の演劇部と芸人による劇の公演や「こうのとりSDGsパートナー」による体験・物販コーナーの出展などがあり、当日は5千人を超える方々に来場いただきました。また、同日より、スマートフォンを使用してSDGsを楽しみながら知り、実践することができるSDGsポイント「ブーケ」の運用を開始しました。持続可能なまちづくりのためには、市民や事業者の皆さんと連携して取り組んでいくことが重要であり、SDGsをより身近なものとして感じられる環境づくりを進めることで、多くの市民や事業者の皆さんがSDGs達成に向けた行動をスタートしていただけたものと考えています。
一方で、昨年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」では、低所得世帯支援枠について給付金の支援を行うとともに、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を引き続き支援するために、重点支援地方交付金の追加が盛り込まれ、12月17日に関連する令和6年度補正予算が成立しました。
本市においても、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰の影響を受けている市民の皆さんをいち早く支援するため、市全体に効果が波及する「こうのす空・花クーポン券2025事業」及び「水道基本料金2か月分免除」を実施します。また、「学校給食食材費の高騰分支援」のほか、「省エネ家電製品買換え促進」及び「住宅等防犯対策」並びに「地域防犯カメラ設置」に対し補助を行います。さらに、住民税均等割非課税世帯への給付金の速やかな支給に向け、現在、第1回目の振込準備を進めているところです。これらの取組を通じて、市民の皆さんのくらしを全力で支援してまいります。
(2)国・県の動向
近年、人口減少・少子高齢化の進行により、産業を支える労働力や地域の担い手の不足などが深刻化しているほか、地球温暖化に伴う気候変動等により、自然災害が激甚化・頻発化しています。
また、行政サービスの提供にあたっては、急速に発展するデジタル技術の活用(DX)やコロナ禍を機に変化したライフスタイルへの対応も求められています。
さらに、経済が進展し、社会の成熟化が進む中で、人々の価値観がこれまでの「物の豊かさ」から「心の豊かさ」を重視する方向へと変化・多様化してきていることを背景に、身体的、精神的、社会的に満たされた状態を表す“ウェルビーイング(Well-being)”の考え方が広く浸透しつつあります。国においても『経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)2024』において、「誰もが活躍できるウェルビーイングが高い社会の実現」を目指す旨を明記するなど、ウェルビーイングの視点による政策展開が進んでいることから、国が公開している本市の指標等を踏まえながら、社会経済環境の変化に伴う様々な課題の解決に向け、持続可能なくらしと社会の実現に取り組んでいく必要があります。
このような中、国では、令和7年度一般会計当初予算案を、昨年12月27日に閣議決定しました。
一般会計の総額は115兆5,415億円で、当初予算として3年連続で110兆円を超え、過去最大となる見通しです。予算案のポイントとしては、「地方こそ成長の主役」との考えのもと、新たな地方創生施策を推進するための交付金を令和6年度当初予算よりもさらに拡充するなど、地方を重視する姿勢が強く打ち出されています。
また、能登半島地震等における教訓・課題等を踏まえ、令和8年度の「防災庁」の設置に向けた体制整備の一環として、災害対応力の強化と事前防災の徹底に向けた取組を進めるほか、こども・子育て政策では、「こども未来戦略」の加速化プランを本格実施することで、全てのこども・子育て世代に対し、切れ目のない支援を行っていくこととしています。
埼玉県では、令和7年度の予算編成において、本県は、人口減少・超少子高齢社会の到来と激甚化・頻発化する自然災害などへの危機対応という、大きな2つの歴史的課題に直面しているとの認識のもと、これらに敢然と立ち向かい、次世代に対する責任を果たすため、「歴史的課題への挑戦」として、社会全体の生産性の向上や持続可能なまちづくり、こどもまんなか社会の実現に向けた子育て支援、人手不足対策等による強い経済の構築など、あらゆる施策を総動員するほか、能登半島地震などの検証を踏まえた入念な備えを進めるとしています。
また、「『日本一暮らしやすい埼玉』の着実な実現」として、社会の在り方が変化し、多種多様な価値観が広がっている中、あらゆる人に居場所があり、活躍でき、安心して暮らせる社会を着実に実現していくとの方向性を示しているところです。これらを踏まえ、「歴史的課題への挑戦と未来への躍進」に向けた施策を実行するため、令和7年度一般会計当初予算案の総額を、過去最大規模となる2兆2,308億9,000万円としています。
(3)市政運営の3つの基本理念
このような国や県の動向を踏まえつつ、本市の令和7年度の予算編成にあたっては、事業の重点化と優先順位の明確化、基金や国庫支出金及び県支出金等の積極的な活用による財源確保や業務効率化を徹底するとともに、「市長と語る地域懇談会」や「市長のまち探検」などを通じて把握した市民や事業者の皆さんのニーズにきめ細やかに対応することで、さらなる行政サービスの向上を目指すこととしました。その上で、令和7年度の市政運営にあたっては、3つの基本理念のもと、第6次総合振興計画後期基本計画に掲げる6つの政策と全28の施策に係る全ての事務事業を着実に推進し、ウェルビーイングの向上を図ってまいります。
基本理念の1点目は、『くらしやすさを実感できるまちづくり』です。
市民が安全で安心な生活を営むためには、激甚化・頻発化する自然災害や身近な犯罪等の生命・財産を脅かす危機に対応し、市民一人ひとりがいきいきと健やかで充実した生活を送ることができる環境とくらしを支える都市基盤が整備されていることが土台となります。
このため、『自助・共助・公助』の考えのもと、市民・自治会・市が連携して地域の災害に対する備えを充実させることで災害対応力を強化するとともに、地域の安全を確保し、安心して生活できる環境を整備するため、市民や自治会・事業者と市が協力し、犯罪の未然防止に向けた取組を拡充するなど、市民の皆さんの安全を守り、安心なくらしを支える取組に注力してまいります。また、市民の皆さんそれぞれのライフステージに応じた健康づくりをはじめ、自分らしく生活できる環境づくりを支援するほか、日々のくらしを快適で利便性の高いものとするため、地域の憩いの場の創出や誰もが移動しやすい交通環境の整備を通じて、都市機能の向上を図ることにより、『くらしやすさを実感できるまちづくり』を進めます。
2点目は、『こども・若者、子育てにやさしいまちづくり』です。
国は「全てのこども・若者の幸せと未来を守る」との考えのもと、こどもまんなかのバージョンアップを掲げ、「こども未来戦略」の加速化プランを本格的に実施していく考えです。
本市においても、こどもまんなか社会の実現を目指し、その根幹となるこどもの権利とその保障について定める「鴻巣市こどもの権利条例」について、本年4月1日施行を目指し準備を進めています。本条例では、11月20日を「こうのす☆こどもの権利の日」とすることで、こどもの権利について、こども、保護者、地域住民等の理解を深めてまいります。
また、本年3月を目途に「鴻巣市こども計画」の策定を進めており、本計画に基づく施策を有機的に展開し、こどもを安心して産み育て、次代を担うこどもたちが健やかに成長していくことができる環境づくりに取り組みます。
さらに、こどもたちの「生きる力」を育むための学びの支援と文化芸術の振興を併せて進めることにより、『こども・若者、子育てにやさしいまちづくり』を進めます。
3点目は、『SDGsの推進による持続可能なまちづくり』です。
本市では、令和5年8月策定の「鴻巣市SDGs未来都市計画」において、2030年のあるべき姿を「人にも生きものにもやさしい コウノトリの里 こうのす」とし、“経済”“社会”“環境”の3つの分野からの事業展開によるSDGsの達成に取り組んでおり、令和6年度は、SDGsパートナー制度の創設やSDGsポイント制度の導入などを通じて、市民や事業者の皆さんとの連携体制の構築を進めてまいりました。
令和7年度は、その成果を基盤として、さらなるステップアップを図るため、令和6年度に創出・拡大した連携の輪をより確かなものにするとともに、コウノトリをシンボルとした本市の取組を市内外に広く発信してまいります。
また、新たな事業活動に挑戦する事業者への支援や農業をはじめとする地域産業拠点施設の整備などを通じた産業振興のほか、脱炭素につながる新しい豊かなくらしを創る国民運動である「デコ活宣言」を本年1月16日に表明したことを契機として、市民や事業者の皆さんと連携しながらゼロカーボンシティの実現に向けた取組を推進します。
このように、本市におけるSDGsの達成に向けた取組を、さらに拡大・深化させていくことにより、『SDGsの推進による持続可能なまちづくり』を進めます。
(4)令和7年度の主な事業展開
新年度における主な取組についてご説明申し上げます。
はじめに、市政運営の3つの基本理念に基づく重点事業について申し上げます。
基本理念の1つ目、『くらしやすさを実感できるまちづくり』の主な取組として、「災害支援体制整備事業」では、避難所の生活環境の抜本的な改善を目的に新設された国の地域防災緊急整備型の「新しい地方経済・生活環境創生交付金」を活用し、備蓄品を充実させるほか、「家具転倒防止器具等設置促進事業」では、新たに、住宅用火災警報器を補助対象に加え、災害時における人命の保護及び防災意識の高揚を図ります。
また、小・中学校の「施設維持管理事業」では、近年の猛暑に対応し、児童・生徒のより良い教育環境の整備と避難所環境の充実のため、学校体育館への空調設備の導入に向けた調査を実施します。
「地域防犯体制支援事業」では、鴻巣駅周辺への防犯カメラの増設をはじめ、新たに、自治会・町内会による防犯カメラの設置を支援する地域防犯カメラ等設置補助金を創設することで、犯罪の未然防止に向けた取組を強化します。また、住宅や店舗、事業所等への防犯カメラや人感センサーライトの設置などの費用に対する補助を継続して実施するほか、公園等の公共施設への防犯カメラ付き自動販売機の設置を進めるなど、地域や民間事業者等と連携した防犯環境の整備を図ります。
「がん対策事業」では、がん患者が自分らしく生活し続けられることを支援するため、新たに、ウイッグ及び補整具等のアピアランスケア用品の購入費用や18歳から30歳代の若年がん患者の在宅療養に必要な生活支援に係る費用の助成を開始します。
「(仮称)北新宿近隣公園整備事業」では、北新宿第二土地区画整理事業地内にインクルーシブ遊具やドッグランなどを備えた公園を整備するため、土地造成工事に着手するほか、四阿・多目的トイレ建築のための地質調査や建築設計を行います。
「公共交通維持事業」では、コミュニティバス「フラワー号」の車両1台をEv車両に更新するほか、持続可能な公共交通体系を構築するため、地域公共交通計画の策定に着手します。
次に、基本理念の2つ目、『こども・若者、子育てにやさしいまちづくり』の主な取組として、「こどもまんなか推進事業」では、こどもの社会参画や意見表明の機会の充実、さらには多様な声の施策への反映に向けて、新たに、こどもの意見を継続的に聴き取るためのチャンネルを構築します。また、こどもの権利についての周知啓発を図り、他の施策や事業とも連携しながら、「鴻巣市こども計画」が掲げる将来像「すべてのこども・若者が自分らしく成長できる こどもまんなか・こうのす」の実現に向けて取り組みます。
「こどもの居場所支援事業」では、給食が提供されない夏休み等の長期休業期間中に、鴻巣女子高校とこども食堂運営団体との協働・連携により、新たに、出張こども食堂を開始します。
また、「吹上地域保育園等新設整備事業」では、保育所と児童発達支援センターに地域子育て支援拠点機能を加えた複合施設として、令和10年4月の開所を目指し、引き続き施設設計を進めます。
「(仮称)川里義務教育学校整備事業」では、川里地域の教育環境に関する様々な課題に対応した新しい時代の学びの場を実現するため、施設一体型の義務教育学校の設置に向け、整備予定地の測量を実施します。
「教育支援センター管理運営事業」では、本年8月を目途に、不登校の児童・生徒に対する支援を充実し、より良い教育環境を整備するため、本年3月31日に閉校となる小谷小学校に教育支援センターを移転します。
また、「適応指導教室活用事業」では、長期にわたり欠席している児童・生徒の自立と学校への復帰を支援する適応指導教室(Let's教室)の開室時間を延長するとともに、登校はできるがクラスに足が向かない児童・生徒への学習支援を行う校内教育支援センター(With)を、新たに、小学校1校、中学校2校に設置することにより、こどもたちの学びの場の確保や居場所づくりを進めます。
「教育相談室活用事業」では、新たに、スクールソーシャルワーカーを増員し、不登校対策の充実を図ります。
そして、基本理念の3つ目、『SDGsの推進による持続可能なまちづくり』の主な取組として、「SDGs推進事業」では、こうのとりSDGsパートナーの交流促進により、市とパートナーとの連携、さらにパートナー同士の連携を深化させるとともに、本年1月25日にスタートしたSDGsポイント「ブーケ」の認知度向上と利用拡大を進めることで、市民や事業者、団体等がSDGsの達成に向けて自発的に取り組んでいくといった行動変容へとつなげていきます。また、2025年日本国際博覧会、通称「大阪・関西万博」での内閣府主催による「地方創生SDGsフェス」への出展や「こうのとりSDGsフェスティバル」の開催等を通じて、コウノトリをシンボルとした本市のSDGs達成に向けた取組を、広く国内外に向けて発信します。
「商工会補助事業」では、地域経済の活性化、雇用の創出、産業の振興を図るため、新たに、経営革新計画策定事業補助金を創設し、経営力の向上のため積極的に経営革新に取り組む事業者を支援します。
「道の駅整備事業」では、にぎわいの創出と地域産業の振興を図る拠点施設となる道の駅の整備に向けた土木工事に着手するほか、アクセス道路の整備を行います。
「エコな住環境づくり事業」では、省エネ基準を達成した家電製品への買換え促進により、家庭におけるデコ活の浸透を図ることで、脱炭素社会の実現を目指します。
このほかの重点事業として、令和7年度は、平成17年10月の鴻巣市、吹上町、川里町の1市2町の合併から20周年を迎えます。合併以降、新市建設計画に位置づけた数々の重点事業を積極的に展開したことにより、本市のまちづくりは大きく進展しています。この節目の年を市民の皆さんとお祝いするとともに、シティプロモーションの効果的な推進による市民のさらなる一体感の醸成や交流の促進を図り、『ふるさと こうのす』への誇りと愛着を育むための記念事業を実施してまいります。
その取組の1つとして、合併20周年を機に、国の特別天然記念物であり、本市になじみが深く、まちづくりのシンボルとしているコウノトリの「市の鳥」指定に向け、準備を進めてまいります。
また、こどもたちが、本市の様々な魅力を知るきっかけづくりとして、夏休み期間中、コミュニティバス「フラワー号」の小・中学生の運賃を無料とするほか、「こうのす☆こどもの権利の日」制定を記念し、「青少年健全育成市民のつどい」において、こうのす観光大使による講演を実施します。
さらに、本市の学校給食や食育の取組への理解を深めるため、市民の日記念献立や地場産食材を使用した献立の提供日に合わせ、小・中学校の保護者を対象とした給食試食会を開催します。
このほか、本市が持つ様々な地域の魅力を再認識し、市内外の多くの方々に発信するため、「こうのす花火大会」及び「鴻巣びっくりひな祭り」への支援を拡充するほか、「こうのす花まつり」と「コスモスフェスティバル」の会場へのフォトスポットの設置や「かわさとフェスティバル」における今昔写真パネル展の開催を予定しています。
また、「合併20周年記念」を冠した市主催イベント等を数多く実施することで、市民の皆さんに合併20周年を幅広く周知し、次の10年のまちづくりに向けた機運の醸成を図ってまいります。
(5)政策ごとの事業展開
続いて、総合振興計画に基づく6つの政策の目標達成に向けて取り組む事業のうち、新規及び一部新規事業や拡充事業を中心に、ご説明申し上げます。
政策1 子育て・教育・文化に関する政策
~未来をひらく人材を育て、確かな学びと文化が根付くまちづくり~
「こどものための安全対策事業」では、保育所等における安全対策として、パーテーションやカメラなどを設置します。
また、「こども家庭センター事業」では、新たに、ヤングケアラーコーディネーターを配置するほか、高校生年代を対象としたヤングケアラーの実態調査を行います。
「小・中学校適正規模及び適正配置事業」では、小・中学校の適正規模及び適正配置の計画に基づき、大芦小学校と吹上小学校との統合に向けた意見交換会等を実施し、方向性を定めます。
「放課後児童クラブ管理運営事業」では、公設公営の田間宮放課後児童クラブ及び馬室放課後児童クラブに入退室管理システムを導入するほか、令和8年度以降の開設を目指し、下忍小学校区内と松原小学校区内への放課後児童クラブの整備を進めます。
「文化芸術振興事業」では、文化芸術振興への持続的な支援等を行うことを目的として、新たに、「鴻巣市文化芸術振興基金」を設置します。
「公共施設予約システム事業」では、システムから予約できる対象施設を拡大した上で、オンライン決済機能を備えた公共施設予約システムの運用を開始します。
政策2 保健・福祉・医療に関する政策
~いきいきと健康で充実した生活を過ごせるまちづくり~
「特定健康診査等事業(国保特会)」及び「後期高齢者健康診査事業」では、健康に過ごす意識を醸成するため、国民健康保険の特定健康診査に加え、後期高齢者医療制度における健康診査の受診者全員を対象としたSDGsポイント「ブーケ」プレゼントキャンペーンを実施します。
「後期高齢者保健衛生普及事業」では、高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業でのハイリスクアプローチにおいて、新たに、民間事業者への委託方式を導入し、実施体制の強化を図ることで、フレイル予防等、高齢者の健康状態の改善に取り組みます。
また、「重層的支援体制整備事業」では、「福祉かけこみ相談ホットライン」として相談体制を強化するとともに、耳が聞こえにくい方からの相談に円滑に対応するため、新たに、軟骨伝導イヤホンを福祉課等の窓口へ設置します。併せて、自治会などの地域支援団体との連携による居場所づくりの支援等を行います。
「ねんりんピック交流大会開催事業」では、令和8年度の「第38回全国健康福祉祭埼玉大会(ねんりんピック彩の国さいたま2026)」におけるソフトボール競技の本市での開催に向け、実行委員会を設立するなどの準備を進めます。
政策3 安全・安心に関する政策
~安全・安心に暮らせるまちづくり~
「交通安全啓発事業」では、引き続き、交通事故の被害を軽減し、命を守る自転車乗車用ヘルメットの着用促進に向け、全年齢を対象に購入費用を助成します。
「AIを活用した交通安全対策事業」では、地理情報提供システム「こうのとりっぷ」に掲載しているAIを活用した交通事故発生リスクの評価・可視化情報の更新を行うほか、道路整備事業での活用を図るとともに、特にリスクの高い危険個所について、必要な交通安全対策を実施します。
また、「水道事業」では、新たに、浄水場施設の統廃合等に向けた基本計画を策定するほか、馬室浄水場配水池の耐震補強設計を行います。
「公共下水道事業」では、新たに、ウォーターPPP・管理・更新一体マネジメント方式の官民連携の導入を目指した導入可能性調査を行います。
政策4 都市基盤に関する政策
~都市機能と豊かな自然が調和した住みよい快適なまちづくり~
「空家等適正管理事業」では、引き続き、老朽化した空き家等の解体を行った方に補助金を交付するほか、本市の空き家等対策の基礎となる「鴻巣市空家等対策計画」を改定します。
道路機能の維持・回復を目的とした「道路改修事業」では、老朽化した舗装の打ち換えや道路排水構造物の更新などを、「幹線道路等整備事業」では、舗装の個別施設計画に基づく幹線道路等の舗装の打ち換えなどにより、安全性と快適性の向上を図ります。
また、「道路改良事業」では、道路拡幅や側溝新設などにより、道路機能の向上を図ります。
「市道A-1004号線整備事業」では、国道17号箕田(南)交差点からフラワー通りに向かう北側約100m区間における歩道整備及び右折帯の設置を行い、道路環境の向上を図ります。
「三谷橋大間線(3期工事)整備事業」では、用地買収及び物件移転補償を行うほか、「荒川左岸通線整備事業」及び「駅南通線整備事業」では、物件調査を行い、事業の進捗を図ります。
「公共下水道事業」では、浸水被害軽減のため、大間2号調整池の整備に向けた基本設計等を行います。
「鴻巣駅東口エレベーター整備事業」では、鴻巣駅東口におけるエレベーター整備に向けた実施設計を行います。
「既設公園施設・遊具改修事業」では、点検により対策が必要とされた遊具や上谷総合公園親水施設のろ過ポンプなどの修繕工事のほか、和式トイレの洋式化を行います。
「コウノトリ飼育施設管理運営事業」では、引き続き、自然と共存する持続可能なまちづくりのシンボルとしてコウノトリのつがいを飼育するとともに、関東地方におけるコウノトリの遺伝的多様性を考慮した繁殖等も検討しながら、将来の放鳥を目指します。
政策5 産業に関する政策
~にぎわいと活力と魅力を創出できるまちづくり~
「市営駐車場管理運営事業」では、鴻巣駅東口駐車場の効果的・効率的な修繕の実施に向け、管理組合と連携して長期修繕計画を策定します。
「鴻巣・行田地区経営体育成基盤整備事業」では、農業生産基盤の整備による生産性の向上を図るため、暗渠排水工事や換地業務等を実施するほか、「渡内糠田排水機場維持管理事業」では、排水機場内の基幹設備である1号ポンプの整備補修を行います。
政策6 市民協働・行政運営に関する政策
~市民協働による一人一人が主役のまちづくり~
「集会所建設等補助事業」では、集会施設の修繕に係る補助対象として、新たに、冷暖房機器の新設・更新等の少額の修繕経費を追加します。
「公共施設等マネジメント事業」では、旧吹上保健センターと旧三谷橋大間線(2期工事)整備事業代替地の売却に必要な不動産鑑定、測量委託等を行うほか、「随意契約保証型民間提案制度ガイドライン」の策定を進めます。
「電子入札共同運営事業」では、これまでの建設工事等の入札に加え、新たに、物品売買等についても埼玉県電子入札共同システムを利用することにより、事務の効率化や入札の透明性・利便性の向上を図ります。
「情報系システム事業」では、サブスクリプション形式によるソフトウェアの導入に対応するため、LGWAN接続系端末から直接インターネット上の特定クラウドサービスへ接続するための環境構築を行います。
「第7次総合振興計画策定事業」では、次期総合振興計画策定に向け、アンケートやワークショップの実施などを通じ、基本構想(案)の策定を進めます。
重点事業及び主要事業の説明は以上となりますが、このほか、6つの政策に基づく主な事業につきましては、別添「令和7年度予算参考資料」のとおりとなっています。
引き続き、令和7年度予算(案)の大綱について申し上げます。
2 予算(案)の大綱
(1)令和7年度予算(案)の基本的な考え方
令和7年度予算の編成にあたりましては、歳出では、高齢化の進行などによる社会保障関係費の増加、賃金や原材料価格の上昇による物価高騰が続く中、持続可能な行財政運営に取り組むことを基本とし、前例主義からの脱却、緊急度・優先度に基づく施策・事業の選択、経費の節減などの徹底に努めています。
一方、歳入では、国の地方財政対策を踏まえ、市税や各種交付金の予算に反映したほか、国庫支出金及び県支出金を最大限に活用した予算としています。
それでは、令和7年度予算の規模と内容について、その概要を申し上げます。
(2)予算規模
令和7年度一般会計予算の総額は、431億3,100万円、令和6年度と比較すると、25億6,300万円、約6.3%の増となり、過去最大の予算規模となります。
1.一般会計歳入
歳入の根幹をなす市税は、市民税では、個人市民税の納税義務者の増加などによる増収を見込み、前年度比4億8,407万円増の80億4,010万5千円とし、また、固定資産税においては、新築家屋数の増加などを見込み、前年度比1億6,080万3千円増の61億8,542万3千円とするなど、市税全体では、前年度比6億7,019万2千円増の158億6,304万7千円としています。
株式等譲渡所得割交付金は、前年度比4,800万円増の1億1,700万円とし、地方消費税交付金は、前年度比4,700万円増の25億5,000万円を計上しています。
地方交付税は、国が示した地方財政対策において、社会保障関係費、人件費の増加や物価高が見込まれる中、地方団体が様々な行政課題に対し、行政サービスを安定的に提供できるよう、令和6年度を上回る額を確保するとしていることから、1億円増の71億2,000万円を計上しています。
また、国庫支出金は、児童手当の支給などに係る負担金、自治体情報システム標準化に係る補助金の増や重層的支援体制整備事業の本格実施などにより、前年度比13億943万2千円増の76億6,614万9千円を計上しています。
県支出金は、国勢調査や参議院議員通常選挙に係る委託金の皆増や重層的支援体制整備事業の本格実施などにより、前年度比3億746万3千円増の34億1,882万1千円を計上しています。
繰入金は、保育所や小・中学校の備品購入費などに充当する森林環境整備基金繰入金では、前年度比1,121万7千円増の1,739万6千円、合併振興基金繰入金では、重点事業である道の駅整備事業への活用として、前年度比7,241万4千円減の1億8,803万2千円、繰入金全体では、前年度比6,119万9千円減の24億1,199万8千円を計上しています。
市債は、臨時財政対策債が皆減する一方、小学校施設改修事業債の増加などにより、1億3,880万円増の7億8,890万円を計上しています。
2.一般会計歳出
次に、歳出を目的別で見ますと、議会費は175万8千円の増、総務費は6億9,769万4千円の増、民生費は17億8,189万8千円の増、衛生費は1億6,691万4千円の増、労働費は2,063万3千円の減、農林水産業費は7,419万2千円の減、商工費は1,651万7千円の増、土木費は2億4,296万3千円の減、消防費は5,815万8千円の増、教育費は2億8,838万4千円の増、公債費は1億1,414万1千円の減となっています。中でも、歳出予算の約46.1%を占める民生費は198億7,684万3千円を計上し、令和6年10月から対象が拡充された児童手当支給事業、民間保育所などの職員の処遇改善により増額となった特定教育・保育所等支援事業、利用者の増加などが続く障害者自立支援給付事業などの各福祉事業における手厚い支援や充実したサービスを実施するための予算としています。
また、総務費では、各種行政手続に係る自治体情報システムを標準化・共通化する基幹系システム事業、教育費では、鴻巣中央小校舎屋上防水等改修工事を実施する小学校施設改修事業などにより増額予算としています。
一方、減額となった費目としては、労働費では、勤労者福利厚生支援事業の減、農林水産業費では、建設発生土搬出の完了による道の駅整備事業での減、土木費では、事業進捗に伴う広田中央特定土地区画整理事業特別会計繰出金の減などが主な要因となっています。
このほか、施政方針に掲げた「3つの基本理念」に基づく重点事業をはじめ、総合振興計画に基づく6つの政策を着実に推進するための予算編成としております。
3.特別会計
次に、特別会計の予算規模についてご説明申し上げます。
国民健康保険事業特別会計については、税率改正により国民健康保険税が増額となる一方、団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行に伴い被保険者が減少していることなどによる医療給付費の減が主な要因となり、117億3,500万円、前年度比10億4,100万円、約8.1%の減となっています。
介護保険特別会計については、介護老人福祉施設などへの入所に係る施設介護サービス給付費の増が主な要因となり、101億1,500万円、前年度比3億6,300万円、約3.7%の増となっています。
北新宿第二土地区画整理事業特別会計については、事業進捗に伴う宅地造成工事や区画道路築造工事などの増が主な要因となり、6億1,100万円、前年度比5,100万円、約9.1%の増となっています。
広田中央特定土地区画整理事業特別会計については、換地計画書作成業務委託料などの減が主な要因となり、7,600万円、前年度比1億1,100万円、約59.4%の減となっています。
後期高齢者医療特別会計については、21億100万円、前年度比200万円、約0.1%の増となっています。
4.公営企業会計
最後に、公営企業会計の予算規模についてご説明申し上げます。
まず、水道事業会計の支出は、収益的支出が23億1,916万5千円、前年度比8,079万5千円、約3.4%の減、資本的支出が13億9,713万4千円、前年度比5,888万2千円、約4.4%の増となっています。
収益的支出の減少は、馬室浄水場及び吹上第二浄水場耐震診断業務委託の減、資本的支出の増加は、馬室浄水場配水池耐震補強設計業務委託、箕田浄水場ろ過ポンプ盤更新工事の増が主な要因となっています。
次に、公共下水道事業会計の支出は、収益的支出が25億2,318万3千円、前年度比1,197万8千円、約0.5%の減、資本的支出が16億768万円、前年度比1億7,950万5千円、約10.0%の減となっています。
収益的支出の減少は、企業債利息の減、資本的支出の減少は、鴻巣停車場線の公共下水道汚水管渠布設替工事の減が主な要因となっています。
次に、農業集落排水事業会計の支出は、収益的支出が1億6,697万1千円、前年度比836万4千円、約4.8%の減、資本的支出が4,462万5千円、前年度比389万4千円、約8.0%の減となっています。
収益的支出の減少は、地方公営企業法適用により費用計上した特別損失の減、資本的支出の減少は、企業債償還金の減が主な要因となっています。
3 『しあわせと生きがいを感じられる“ウェルビーイング”なまちづくり』に向けて
令和7年度は、平成17年10月の鴻巣市、吹上町、川里町の1市2町の合併から20周年となる節目の年です。
本市の人口は微減の状況にありますが、社会動態では平成27年から令和6年まで10年連続で転入超過が続いており、都市基盤の整備や交通の利便性向上、こども・子育て支援、教育環境の整備、福祉施策の充実など、新市建設計画を基礎とした「第6次鴻巣市総合振興計画」に基づく取組の成果が、着実に花開いているものと考えています。
私は、この流れをさらに加速させるべく、強い決意と覚悟を持って、新年度の市政運営を推進してまいります。
本市のさらなる発展と飛躍に向け、「市民と歩む新しい鴻巣」を基本姿勢として、各事業の着実な進捗を図り、誰一人取り残さない持続可能な市政運営を進めることで、市民の皆さん一人ひとりが主役となり、しあわせと生きがいを感じられる“ウェルビーイング”なまちづくりに向け、全力で取り組んでまいります。
議員各位、市民の皆様におかれましては、令和7年度においても、引き続き、格別のご理解とご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、新年度にあたっての私の所信といたします。