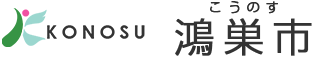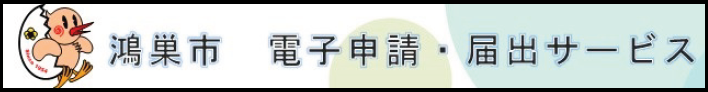本文
子どもの定期予防接種
予防接種法で定められている定期予防接種を個別に医療機関で受けることができます。
出生後・転入後に予防接種の案内を郵送しています。対象の年齢・期間であれば無料で接種ができます。市から郵送された「予防接種と子どもの健康」や通知をよく読み、事前に医療機関に予約のうえ、予防接種を受けてください。
通知が届かない方や予診票を紛失された方、転入されてすぐに予防接種を予定されている方は、保健センターで発行が可能です。母子健康手帳を持って保健センターまでお越しください。
予防接種の種類・対象期間・回数
鴻巣市に住民登録のある、下の表の対象年齢にある方が対象です。
|
ロタウイルス (2種類あります) |
1価ロタワクチン(ロタリックス) 生後6週0日から生後24週0日まで 回数:2回 5価ロタワクチン(ロタテック) 生後6週0日から生後32週0日まで 回数:3回 標準的な接種開始時期は、生後2か月から |
|---|---|
|
B型肝炎 |
1歳のお誕生日前日まで 回数:3回 標準的な接種年齢:生後2か月から9か月 |
|
小児用肺炎球菌 |
生後2か月から5歳の誕生日前日まで 標準的な接種開始時期:生後2か月から7か月 回数:1回から4回 注意:接種開始年齢等によって回数が異なります |
| ヒブ |
生後2か月から5歳の誕生日前日まで 標準的な接種開始時期:生後2か月から7か月 回数:1回から4回 注意:接種開始年齢等によって回数が異なります |
|
4種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ) |
生後2か月から7歳6か月になる前日まで ・第1期初回 標準的な接種年齢:生後2か月から12か月まで 回数:3回 ・第1期追加 標準的な接種期間:第1期初回3回接種終了後1年から1年半までの間隔をおく 回数:1回 |
|
5種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ・ヒブ) 【令和6年4月1日から使用開始】 |
生後2か月から7歳6か月になる前日まで ・第1期初回 標準的な接種年齢:生後2か月から12か月まで 回数:3回 ・第1期追加 標準的な接種期間:第1期初回3回接種終了後1年から1年半までの間隔をおく 回数:1回 |
| BCG |
1歳の誕生日の前日まで 標準的な接種年齢:生後5か月から8か月 回数:1回 |
| 麻しん風しん混合 (MR) |
・第1期/1歳から2歳の誕生日前日まで 回数:1回 ・第2期/小学校入学前の1年間 回数:1回 注意:令和6年度の麻しん風しん混合ワクチン第2期対象は平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方です。(令和6年3月31日まで) |
| 水痘(水ぼうそう) |
1歳から3歳の誕生日の前日まで 回数:2回 注意:水痘(水ぼうそう)にかかったことのある方は、接種の対象となりません。 |
| 日本脳炎 |
・第1期初回 生後6か月から7歳6か月になる前日まで 標準的な接種年齢:3歳から4歳 回数:2回 ・第1期追加 生後6か月から7歳6か月になる前日まで 標準的な接種年齢:4歳から5歳 回数:1回 ・第2期 9歳から13歳の誕生日前日まで 標準的な接種年齢:9歳から10歳 回数:1回 注意:平成19年4月1日以前までの生まれの方は、20歳の誕生日前日まで接種することができます。 |
|
二種混合(ジフテリア・破傷風) |
11歳から13歳の誕生日の前日まで 標準的な接種年齢:11歳から12歳 回数:1回 注意:予診票は11歳の誕生日翌月に郵送します。 |
| 子宮頚がん |
小学校6年生から高校1年生相当の女子 標準的な接種年齢:中学1年生 回数:3回 中学1年生には令和7年4月下旬に予診票を発送します。 |
実施医療機関
県内委託医療機関では市内委託医療機関と同様に無料で接種できます。
県内委託医療機関は、埼玉県医師会ホームページ「住所地外定期予防接種相互乗り入れ 一般」<外部リンク>から確認ができます。
費用
無料
持ち物
- 母子健康手帳
- 記入した予診票
- マイナンバーカードなどの住所が確認できるもの
市外・埼玉県外で予防接種を希望される場合
市外・埼玉県外で予防接種を希望される方は、予防接種を受ける前に「予防接種依頼書」の申請をお願いします。
予防接種依頼書について
予防接種依頼書は、鴻巣市から予防接種を受ける医療機関などに対して、予防接種を依頼する書類です。鴻巣市と契約を結んでいない医療機関で予防接種を受けた際に、予防接種事故(副反応など)が起こった場合の救済を受けるために必要なものです。
予防接種依頼書が必要な場合
- 埼玉県外での定期予防接種(里帰り先での接種など)
- 埼玉県内の住所地外予防接種相互乗り入れ一覧に掲載されていない医療機関で定期予防接種を希望される場合
対象となる定期予防接種の種類
ヒブ、小児用肺炎球菌、ロタウイルス、B型肝炎、4種混合、5種混合、BCG、麻しん風しん混合(MR)、水痘、日本脳炎、二種混合、子宮頸がん
任意予防接種については、こちらのページをご確認ください。
申請方法
以下のいずれかの方法で予防接種依頼書を申請することができます。
(オンラインで申請する場合は、↑の画像をクリックまたはタップしてください。)
詳しい申請方法は、リンク先でご確認ください。
2.窓口で申請
保健センターへお越しいただいて申請していただきます。
申請書は保健センターの窓口でご記入いただきます。
3.郵送で申請
申請書をご記入いただき、健康づくり課へご郵送ください。
記入例も併せてご確認ください。
予防接種依頼書申請書 (PDF:47.3KB)
予防接種依頼書申請書の記入例 (PDF:379.7KB)
申請の際の注意
接種予定日の2週間前までに申請をお願いします。
予防接種を受けるときに、医療機関へ予防接種依頼書を提出していただく必要があります。依頼書が、お手元に届くまでに2週間程度のお時間をいただきますので、お早めに申請をお願いします。
助成金の申請について
依頼書を使って予防接種を受けた場合、接種費用を医療機関窓口で全額自己負担後、保健センターで助成金の申請をしていただくことで、自己負担していただいた予防接種費用を助成します。
任意予防接種についても費用助成をしています。
助成額
定期予防接種費用は全額 ※助成額には上限があります。
申請に必要なもの
- 母子健康手帳
- 予診票
- 領収書(予防接種ごとの費用がわかる明細書など)
- 通帳またはキャッシュカード(振込先のわかるもの)
申請期限
予防接種を受けてから1年以内
依頼書と助成金の申請の流れ
予防接種に保護者が同伴できない場合の対応について
- 16歳未満のお子さまの予防接種に保護者以外の方が同伴する場合
予防接種は、まれに接種後に体調の変化等があることから、接種の際は、保護者の同伴を必要としています。しかし、保護者が特段の理由で同伴することができず、かわりにお子さんの健康状態を普段から熟知する親族等代理の人が同伴する場合は、委任状を作成し、接種当日にご持参ください。
- 18歳未満のお子さんが本人のみで接種する場合
「予防接種は原則、保護者の同伴が必要です。」ただし、16歳以上18歳未満の方で、日本脳炎および子宮頸がん予防ワクチンを受ける場合、保護者が予診票の記載事項を読み、納得してあらかじめ接種することについて同意を得られ、保護者の同意書を医療機関に持参すれば、保護者が同伴しなくても予防接種を受けることができます。
※16歳以上18歳未満のお子さんは、法律上は保護者の同意なく接種することができますが、急な体調変化に対応できるよう、同意書の提出をお願いいたします。
※※予診票の自署欄は、接種を受ける人が16歳以上の場合は、本人が記入できます。使用する予診票の自署欄が「保護者自署」となっている場合、「被接種者自署」と読み替えてご使用ください。