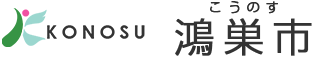本文
農地等の権利移転・納税猶予制度・農業者年金
農地等の権利移転
農地等の権利移転(売買・贈与)
農地を農地として利用することを目的として売買・贈与等により所有権等の権利を取得するためには、農業委員会の農地法第3条許可が必要です。
申請の手続き
受付締切日は、毎月10日(土日祝日の場合は翌開庁日)です。
農地等の権利移転については申請する前に農業委員会事務局に相談してください。
許可を受けるための要件
農地法第3条の許可を受けるためには、次の全ての要件を満たすことが必要になります。
- 全部効率利用要件・・・申請の農地を含め、所有している農地や借り受けている農地のすべてを耕作していること。
- 所有適格法人要件・・・法人の場合は、農地法に規定する農地所有適格法人の要件を満たすこと。
- 農作業常時従事条件・・・個人の場合は、申請者またはその世帯員が農作業に常時従事(年間150日以上)すること。
- 地域との調和要件・・・申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
許可申請に必要な書類
- 農地法第3条許可申請書審査表・添付書類 <1部提出> (Excel:17KB)
- 農地法第3条の規定による許可申請書 <3部提出> (Word:42KB)
- 農地法第3条の規定による許可申請書(別添)<1部提出> (Word:82KB)
- 農地所有適格法人としての事業等の状況(別添)<法人の場合 1部提出> (Word:74KB)
農地等の権利移転(相続)
鴻巣市農業委員会では、農家台帳の整備のため農家世帯に経営主を定めており、経営主宛に調査を行います。そのため、経営主が被相続人のままとなっている場合は、農業経営主変更届を届出してください。
また、平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地を相続等で取得したときは、農業委員会への届出が義務化されました。詳しくはお問い合わせください。
農地の相続税・贈与税の納税猶予制度
農業を営んでいた方が死亡し、農地を相続した方が今後とも農業を営んでいく場合、一定の要件を満たせば農地の相続税の一部が猶予されます。制度について詳しくは管轄の税務署までお問い合わせください。
納税猶予を受けるためには農業委員会が発行する証明の添付が必要となります。発行までにはお時間がかかりますので、余裕をもって申請してください。
申告の手続きの際
納税猶予の申告の手続きの際には、相続税の納税猶予に関する適格者証明書が必要となります。
受付締切日は、毎月10日(土日祝日の場合は翌開庁日)です。農業委員会総会(毎月25日前後)にて許可されてからの発行となります。提出書類等、詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
納税猶予期間中の継続届出の際
納税猶予期間中は相続税の申告期限から3年目ごとに、引き続き農業経営を行っている旨の証明書が必要となります。
受付は随時行っておりますが、発行までに最長で2週間ほど経ってからの発行となります。提出書類等、詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
農業者年金
年間60日以上農業に従事する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)の方、又は60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者(保険料納付免除者を除く)の方であれば、どなたでも加入できます。
- 積立方式(確定拠出型)の年金です。
- 保険料の額は、月額2万円(ただし、35歳未満かつ政策支援加入の対象とならない方は月額1万円)~6万7千円の間で、千円単位で自由に決められます。
- 保険料は全額が社会保険控除の対象で、支払われる年金にも公的年金等控除が適用されます。
詳しくは、農業委員会またはお近くの農協にお問い合わせください。