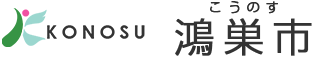本文
同和問題(部落差別)の解決をめざして
同和問題(部落差別)をご存知ですか?
同和問題とは
同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で生み出され、特定の地域の出身であるという理由で、就職や結婚、その他さまざまな場面で差別を受ける、我が国固有の重大な人権問題です。
同和地区(被差別部落)を理由とした差別は「部落差別」ともいわれます。
同和問題の歴史
同和問題は、日本社会の歴史的発展の過程でつくりあげられた身分制度により生み出されたといわれています。
江戸幕府が崩壊し、明治4年8月に太政官布告第61号(いわゆる解放令)が発布されましたが、単に身分の称号廃止と職業の自由を宣言したのにとどまり形式的なものであったため、周囲からの偏見や差別はそのまま放置され、今日まで同和問題を残す要因となりました。
詳細は、埼玉県ホームページをご確認ください。
埼玉県ホームページ(啓発冊子「同和問題の解決をめざして」)<外部リンク>
同和問題(部落差別)に関する様々な人権問題
事例1 結婚・就職等における差別
同和地区出身であることなどを理由に結婚に反対されたり、就職等において不利な取り扱いを受けるなどの事案が発生しています。
事例2 差別落書き・ビラまき・インターネットへの掲載
同和問題に関する差別的な落書きがされたり、ビラがまかれるといった事案が発生しています。
特に近年は、インターネット上で、不当な差別的取り扱いを助長・誘発する目的で特定の地域を同和地区であると指摘するなどの事案も発生しています。インターネット上の情報は、一度拡散してしまうと完全に削除されることが難しいため、問題となっています。
事例3 差別につながる身元調査等
出身地を調べたり、特定の地区が同和地区かどうか調査したりするなどの事案が発生しています。こうした調査は、不当な差別的取り扱いにつながりかねないものです。
事例4 えせ同和行為
「同和問題はこわい問題であり、できれば避けたい」との誤った意識を悪用して、高額の本を売りつけたり、寄付金を強要するなど、同和問題の解決を口実に、企業・行政機関等に「ゆすり」「たかり」等不当な要求をする行為です。
「えせ同和行為」は、同和地区出身者等に対する偏見を助長し、同和問題(部落差別)の解決を阻む大きな要因となっています。
同和問題の早期解決に向けて
これまで、同和問題の解決をめざし様々な事業が行われ、同和地区における生活環境などについては、大きく改善が図られました。
しかしながら、今なお、一部の人に同和問題に係る差別意識や偏見が残っており、差別的な発言や落書き、結婚などの際の身元調査等が行われています。
また、情報化社会の進展に伴い、インターネットの掲示板などに差別的な書き込みや文章を載せる事例も後を絶ちません。
同和問題は「そっとしておけば、自然に消滅するのではないか」という意見が聞かれます。しかし本当にそうでしょうか。明治4年(1871年)の解放令から150年あまりが経過した今も差別が存在する現実があることは、差別は風化しないことを物語っています。
私たち一人ひとりが同和問題を正しく理解し、自分自身の問題として考え、差別を許さないという強い意志を持って行動することが大切です。
「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました
平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。この法律では、部落差別は許されないものであることを明確にし、部落差別のない社会を実現することを目的としています。
「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」が施行されました
令和4年7月8日に「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」が施行されました。この条例では、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにし、部落差別のない社会を実現することを目的としています。
部落差別禁止を規定
- 図書、地図その他資料の公表又は流布
- インターネットの利用による情報の提供
- 結婚又は就職に際しての身元の調査
- 土地建物等を取引の対象から除外するための調査その他の行為
により部落差別を行ってはいけません。
県、県民、事業者の責務を規定
部落差別のない社会を実現するために、県、県民、事業者の責務を定めました。
県条例詳細(埼玉県ホームページ)<外部リンク>
部落差別を解消し、お互いの人権が尊重される社会の実現をめざしましょう。
法務省ホームページ<外部リンク>