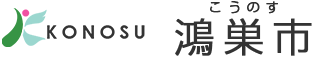本文
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営し、保険料率の決定、賦課額の決定、医療費の給付などの事務や財政運営を行います。
市町村では、後期高齢者医療制度の窓口として、申請や届出の受付、保険料の徴収などを行います。
埼玉県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
対象者
75歳以上の方
75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります。
鴻巣市に転入してきた75歳以上の方
鴻巣市への転入日から後期高齢者医療制度の対象となります。
65歳以上74歳以下で一定の障がいがある方
窓口で申請をしていただき、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から、後期高齢者医療制度の対象となります。
障がい認定の基準
以下の年金の受給権または手帳を取得している方が対象となります。
- 障害基礎年金1・2級
- 身体障害者手帳1・2・3級
- 身体障害者手帳4級のうち、音声機能または言語機能の障がいがあるとき
- 身体障害者手帳4級のうち、下肢障がいで以下に該当するとき
- 1号(両下肢すべての指を欠くもの)
- 3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
- 4号(1下肢の機能の著しい障がい)
- 療育手帳A・(A)
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
被保険者証
※令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなりますが、12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、記載事項に変更が生じなければ、その有効期限(令和7年7月31日)までご使用いただけます。
資格確認書
令和6年12月2日以降、「年齢到達や転入により新規で資格を取得された方」や「現行の保険証の券面事項に変更が生じた方」には、一斉更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を職権で交付します。
|
令和6年12月1日まで |
令和6年12月2日~令和7年7月31日 | 令和7年8月の一斉更新から |
|---|---|---|
| 現行の保険証を交付 | マイナ保険証の有無に関わらず「資格確認書」を交付 |
マイナ保険証をお持ちでない方 →「資格確認書」を交付 |
|
マイナ保険証をお持ちの方 →「資格情報のお知らせ」を交付 |
75歳の誕生日をむかえる方
75歳の誕生日のおよそ半月前までに誕生日当日から有効となる資格確認書が郵送で交付されます。
鴻巣市に転入してきた75歳以上の方
鴻巣市への転入手続き後、転入日から有効となる資格確認書が郵送で交付されます。
(資格確認書の交付までの間は、窓口でお渡しする「後期高齢者医療被保険者関係事項証明書」をご使用ください。)
鴻巣市内で転居された75歳以上の方
転居の手続き後、資格確認書が郵送で交付されます。
(資格確認書の交付までの間は、窓口でお渡しする「後期高齢者医療被保険者関係事項証明書」をご使用ください。)
65歳以上74歳以下で一定の障がいがあり、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
窓口にて申請後、申請日から有効となる資格確認書が窓口または郵送で交付されます。
(資格確認書の交付までの間は、窓口でお渡しする「後期高齢者医療被保険者関係事項証明書」をご使用ください。)
- 資格確認書が届きましたら、記載内容を確認してください。
- 内容を書き換えた資格確認書は使用できません。
- 資格確認書の貸し借りは禁止されています。
- コピーした資格確認書は使用できません。
医療機関窓口での自己負担
医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部を負担していただきます。
一般の方は1割負担です。
また、現役並みの所得のある方は3割負担です。
令和4年10月1日から一定所得のある方は2割負担になります。詳細については、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)医療費の窓口負担割合が変わりますをご覧ください。
現役並みの所得のある方とは・・・
住民税課税所得145万円以上の所得のある被保険者がお一人でもいる世帯は、その同じ世帯にいるすべての被保険者が、一定以上(現役並み)所得者となり、自己負担の割合は「3割」となります。
ただし、前年の被保険者の収入の合計金額が
- 被保険者お一人の世帯の場合・・・383万円未満
- 被保険者お二人以上の世帯の場合・・・520万円未満
の方は、認められると「2割」負担になります。
また、被保険者がお一人の世帯であって、同じ世帯に70歳から74歳の方がいる被保険者については、以下の3点すべてに該当する場合には、認められると「2割」負担になります。
- 被保険者の住民税課税所得が145万円以上
- 被保険者の前年の収入が383万円以上
- 被保険者及び同じ世帯にいる70歳から74歳の方の前年の収入の合計額が520万円未満
一部負担金の減免
災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金の支払が困難と認められる場合には、申請により一部負担金の減額またはその支払の免除を受けられる場合があります。